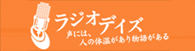二宮清純の視点
二宮清純が探る新たなるスポーツの地平線
2026.01.22
後編 平和都市・広島の使命
~誰もが「諦めない」という選択肢を~(後編)
 伊藤数子(「挑戦者たち」編集長): NPO法人FOOT&WORKは、「車椅子ソフトボール&フレンドリーマッチ in Hiroshima」を主催しています。2023年にスタートして昨年10月に第3回大会を開催しました。私も第2回大会に伺いましたが、笑いが絶えない賑やかなイベントでした。この大会を始めたきっかけは?
伊藤数子(「挑戦者たち」編集長): NPO法人FOOT&WORKは、「車椅子ソフトボール&フレンドリーマッチ in Hiroshima」を主催しています。2023年にスタートして昨年10月に第3回大会を開催しました。私も第2回大会に伺いましたが、笑いが絶えない賑やかなイベントでした。この大会を始めたきっかけは?
下原唯千夏: 広島で車椅子バスケットボールのイベントをした際、手伝いに来てくれたのが一般社団法人日本車椅子ソフトボール協会理事の下川友暉君でした。彼自身は車椅子ユーザーではないのですが、日本代表コーチを務めています。下川君の紹介で広島の車椅子ソフトボールチームに所属し、日本代表としてワールドシリーズ優勝に貢献した江南聖選手と会いました。「ぜひ車椅子ソフトボールを生で観てみたいから、広島でイベントしてください」と話すと、「場所がないんです」と返ってきました。県内にスポーツ施設はたくさんありました。それで場所なら確保できるものと思ったのですが、江南選手に聞くと「下が柔らかいところでは車椅子を全力で動かせません」と言うんです。
 二宮清純: 地面は硬い方がいいんですね。
二宮清純: 地面は硬い方がいいんですね。
下原: そうですね。「ワールドシリーズなどの試合はどこでやっているんですか」と聞いたら、「広い駐車場です」と。日本にも大型スーパーの駐車場がいくつかあると思ったら、車止めや植栽があり、50メートル四方のスペースを確保できないそうなんです。だから会場の確保も一苦労でした。ようやく見つけた広島みなと公園を借りようとした際も、窓口である県の港湾委員会に認めていただくまでにとても時間がかかりました。
二宮: 前例があまりないからでしょうね。
下原: 私たちが言われたのは、「ボールが飛ぶから危ない」という理由でした。だから、理解してもらうのがすごく大変で、外野フェンスの外にフェンスをつくり、そこに人を配置するなどの策を講じました。本当に何度も心が折れかけました。
【心の支えとなった約束】
伊藤: そんな中、「車椅子ソフトボール&フレンドリーマッチ in Hiroshima」に協賛しているスポンサー企業・団体がたくさんあります。これも下原さんの努力の賜物ですね。
二宮: 下原さんの営業力はすごいですね。
下原: いえいえ。ただただ必死で(笑)。場所を借りるのも大変でしたが、協賛集めもすごく大変でした。車椅子ソフトボールという競技を説明するところから始まり、なかなか理解を得られなかった。でも、2回、3回と繰り返すうちに、「去年のやつだね」「今年もやるんだね」と言って、協力してくださる方が増えていったんです。
伊藤: 車椅子競技は、競技用の車椅子を集めるのが至難の業です。「車椅子ソフトボール&フレンドリーマッチ in Hiroshima」では、協賛社が車椅子を寄付くださるケースもあるそうですね。
下原: 本当にありがたいことです。大会開催準備をしたことで、競技用の車椅子を集めるのがいかに大変かということがよくわかりました。
 伊藤: 様々な困難に遭っても踏ん張れたのは、何が理由だったのでしょう?
伊藤: 様々な困難に遭っても踏ん張れたのは、何が理由だったのでしょう?
下原: 車椅子ソフトボールに関わるきっかけとなった下川君と大会を開催する約束をしたからです。その約束をどうしても守りたかった。大会開催するために動いたことで、どれだけ車椅子競技をすることが難しいかを知りました。でも大会を開催することで、この広島というまちから、いろいろなことができる可能性を示したかった。原爆から復興した平和都市としての側面だけでなく、インクルーシブな社会を目指す取り組みを続けていくことがこのまちの使命だと思ったんです。
伊藤: 大会は第4回、第5回と続けていかれると思いますが、今後はどんな展開を考えていますか?
下原: ギャラリーを増やすことに、力を入れていきたいと思っています。例えばパラスポーツに限らず、他のイベントと一緒に開催できれば、そのイベント目当てに来た人がふらっと観に来られると思うんです。そうすれば車椅子ソフトボールにも興味を抱いてもらえるかもしれないし、体験会に参加してくれる可能性もある。ギャラリーが増えれば、選手たちのモチベーションになります。車椅子ソフトボールの大会だけではなく、ひとつのお祭りのようなイベントとして、たくさんの人が集まり、楽しめるものにしたいと考えています。

(おわり)
<下原唯千夏(しもはら・いちか)プロフィール>
NPO法人FOOT&WORK理事長。1965年、広島県出身。1988年、安田女子大学卒業後、医療法人せのがわに入職。公認心理士、精神保健福祉士として、心理療法や精神障害者施設の運営に携わる。2003年、地域の高齢者精神障がい者福祉、メンタル不調者・不登校の支援を通して、生活環境の向上を目指す事業を行うNPO法人FOOT&WORKを設立。誰でも参加できるスポーツイベントや、障がい者向けのスポーツイベントを企画・運営している。2007年、医療法人せのがわの理事長に就任。好きな言葉は、「才能は有限、努力は無限」。好きなスポーツはテニス。
協力 広島県東京事務所
(構成・杉浦泰介)