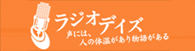二宮清純の視点
二宮清純が探る新たなるスポーツの地平線
2010.09.23
第4回 遊びは子供たちの学びの場
~障害者スポーツの未来を考える~(4/5)
二宮: 日本のスポーツを考えるうえで欠かせないのが子供たちの環境です。河合さんは5歳から水泳をやっていたという話ですが、ひと昔前まではスポーツは子供の遊びの一環でした。ところが、今はテレビゲームや携帯電話などの普及によって、外で体を動かすことが随分と減ったように感じます。もちろんテレビゲームや携帯電話が悪いとは言いません。しかし、外で子供たちの声が聞こえないというのは、なんとも寂しい話です。

河合: 現場にいても、確かにそういう遊びの環境の変化は感じましたね。私が中学校の教師をしていた時、生徒に日記を書かせていました。すると、こんなことが書いてあったんです。「昨日、友達と遊びました。友達の家で一緒にマンガを読みました」。いやぁ、驚きましたね。だって、マンガって一人で読むものじゃないですか。だったら、借りてきて自分の部屋で読んでるのと変わらない。それを「遊び」として捉えているんだということを知って、衝撃を受けました。今の子供たちは同じ時間、同じ空間に一緒にいさえすれば「遊んだ」ということになるのでしょうね。「遊び方を教えなければいけない」なんていう言葉を聞くと、本当に悲しくなります。
二宮: 昔は遊ぶことでルールを覚えたり、人とのつながりをもつことができました。
河合: そうですね。遊びの延長であるスポーツにも同じことが言えます。上下関係があったり、同じ目標をもって切磋琢磨したり......。子供たちには遊びやスポーツを通じてさまざまな意識を高めていってほしいと思います。
 二宮: 今回、文部科学省が発表した「スポーツ立国戦略」には、その部分が抜け落ちていると思うんです。つまり、遊びを通して子供たちはさまざまなことを学び、果ては情操教育にもなるということが触れられていない。例えば、現代人に不足していると言われるコミュニケーション。子供がキレやすくなった要因のひとつには、コミュニケーションの方法を知らず、どうやって人に自分の気持ちを伝えていいかわからないからだとも言われています。遊びにはコミュニケーション能力を高める要素がたくさん含まれている。そもそもコミュニケーションなしでは遊ぶことはできませんからね。「スポーツ」の語源は「遊び」であることからも、「スポーツ立国戦略」にも、もっと「遊び」が盛り込まれるべきではないでしょうか。
二宮: 今回、文部科学省が発表した「スポーツ立国戦略」には、その部分が抜け落ちていると思うんです。つまり、遊びを通して子供たちはさまざまなことを学び、果ては情操教育にもなるということが触れられていない。例えば、現代人に不足していると言われるコミュニケーション。子供がキレやすくなった要因のひとつには、コミュニケーションの方法を知らず、どうやって人に自分の気持ちを伝えていいかわからないからだとも言われています。遊びにはコミュニケーション能力を高める要素がたくさん含まれている。そもそもコミュニケーションなしでは遊ぶことはできませんからね。「スポーツ」の語源は「遊び」であることからも、「スポーツ立国戦略」にも、もっと「遊び」が盛り込まれるべきではないでしょうか。
河合: 昔は自然と遊んでいましたから、特にそういうことを考えなくてもよかったのでしょうが、兄弟がいなかったり、近所に子供が少ないなど、私たちとは違う環境があることも事実ですからね。国が積極的に働きかけていくことも必要でしょう。
長所を活かす発想
二宮: 河合さんは実際に教育現場にいたわけですが、子供たちのコミュニケーションについてはどう感じていましたか?
 河合: 確かに一人で遊ぶツールが増えてきた分、コミュニケーション不足は生じてきているとは思いますね。ただ、昔だってコミュニケーションが苦手な子供は少なからずいましたから、何が一番いい方法なのかは正直わかりません。一ついえるのは、それぞれの良さをどう評価するのかが一番重要ということです。例えば、自閉症の子は他人と協調することが難しく、スポーツが苦手な傾向が強いのですが、逆にそういう部分に優れている自閉症の子もいるんですね。ですから、偏った見方をせずに、それぞれのいいところを活かしていくという発想が必要かなと思います。
河合: 確かに一人で遊ぶツールが増えてきた分、コミュニケーション不足は生じてきているとは思いますね。ただ、昔だってコミュニケーションが苦手な子供は少なからずいましたから、何が一番いい方法なのかは正直わかりません。一ついえるのは、それぞれの良さをどう評価するのかが一番重要ということです。例えば、自閉症の子は他人と協調することが難しく、スポーツが苦手な傾向が強いのですが、逆にそういう部分に優れている自閉症の子もいるんですね。ですから、偏った見方をせずに、それぞれのいいところを活かしていくという発想が必要かなと思います。
二宮: 同感ですね。河合さんがそのような考え方をするようになったきっかけは、やはりご両親の影響でしょうか。
河合: 子どもの頃から割と何でも前向きに考えられる性格でしたね。やはり両親の影響が大きかったと思います。それが、いろいろな人に出会うことで、どんどん強化されてきているんでしょうね。
(第5回につづく)
<河合純一(かわい・じゅんいち)プロフィール>
1975年4月19日、静岡県出身。5歳で水泳を始め、パラリンピックにはバルセロナから5大会連続出場。金5個、銀9個、銅7個の計21個ものメダルを獲得した。先天性ブドウ膜欠損症で生まれつき左目の視力がなく、15歳の時に右目も失明し全盲となる。しかし、教師への夢を諦めず、早稲田大学卒業後の98年には母校の舞阪中学に社会科教諭として赴任。2008年からは静岡県総合教育センター指導主事を務めた。今年7月の参議院選挙にはみんなの党から静岡選挙区で出馬。惜しくも次点で落選するも、今後もみんなの党の一員として活動し、政界に一石を投じる。現在、日本パラリンピアンズ協会会長を務める。
河合純一氏のブログはこちらから
◇Keeping Alive The Dreams
(構成・斎藤寿子)