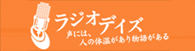二宮清純の視点
二宮清純が探る新たなるスポーツの地平線
2025.01.16
前編 人生の幅を広げるデバイス
~誰もが挑戦できる社会に~(前編)

株式会社ニコ・ドライブは<移動格差の解消>を目指し、下肢障がい者向けの手動運転補助装置「ハンドコントロール」、手動式車椅子に着脱できる電動アシスト装置「HARIDE」「Kanny」「MIJO」などを製造・販売している。同社の代表取締役を務める神村浩平氏に事業の手応えと今後の展望について訊いた。
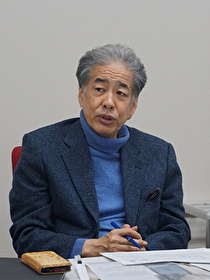 二宮清純: 神村さんは16歳で交通事故に遭い、脊髄を損傷して以来車椅子を使用して生活されています。その後、車椅子バスケットボールを始め、アメリカに留学した経験が人生観を大きく変えたそうですね。
二宮清純: 神村さんは16歳で交通事故に遭い、脊髄を損傷して以来車椅子を使用して生活されています。その後、車椅子バスケットボールを始め、アメリカに留学した経験が人生観を大きく変えたそうですね。
神村浩平: その通りです。向こうでは障がいのある方の多くが車を改造せず、後付けの装置を付けて運転していたんです。中には私よりも年下で17、18歳の子もいました。まずそれにカルチャーショックを受けましたね。"車がこれだけ身近だと10代後半から自立できるんだな"という現実を目の当たりしました。チームでは10人乗り1台の車を借り、後付けの装置を取り付ければ障がいのある方が運転して遠征に行くこともできました。その時に"障がい者も健常者と同じ行動の仕方ができれば、人生の幅が広がるんだ"と感動しました。
伊藤数子(「挑戦者たち」編集長): その経験が「ハンドコントロール」の製造・販売に繋がったんですね。
神村: はい。「ハンドコントロール」そのものを製品化したのは日本の本田技研工業株式会社のエンジニアだった荒木正文さんです。帰国後、そのことを知った私は荒木さんのことをインターネットで調べました。荒木さんのブログには「自分が開発した技術を販売してくれる人を探しています」と書かれていたので、すぐに連絡して「私にやらせてください!」と思いを伝えました。それを機に荒木さんが造り、私が売るという役割分担になったんです。
【操作が簡単なのが利点】
 伊藤: そこからニコ・ドライブ設立に繋がっていくわけですね。
伊藤: そこからニコ・ドライブ設立に繋がっていくわけですね。
神村: ええ。荒木さんは私と出会って1年後に亡くなられました。亡くなる半年前、私は荒木さんが末期のガンであることを知りました。そこで製造部門も託され、荒木さんの思いを引き継ぐかたちで、法人化をして製造体制も整えました。荒木さんには「なるべく世の中に広がることで、障がい者の自立を促したい」という思いがあったので、誰でも造れるように、と会社を立ち上げる際に特許年金の納付を取り下げました。
二宮: 先ほど、手動式車椅子に着脱できる電動アシスト装置「MIJO」を付けた車椅子に試乗しましたが、これは障がいのある人のみならず、高齢の方の移動も助けてくれますね。
伊藤: 電動車椅子と比べても操作が簡単なのがいいですね。「ハンドコントロール」もそうですが、簡単であるのは、とても大事なことです。
 神村: ありがとうございます。「ハンドコントロール」はアクセルとブレーキを持ち手が1本で運転できるんです。押せばブレーキで、引っ張ればアクセルがかかる仕組みになっています。片手でハンドルを持ち、もう一方の手でアクセル・ブレーキ操作ができる。指を引っ掛ける程度ですから、そこまで握力もいりません。
神村: ありがとうございます。「ハンドコントロール」はアクセルとブレーキを持ち手が1本で運転できるんです。押せばブレーキで、引っ張ればアクセルがかかる仕組みになっています。片手でハンドルを持ち、もう一方の手でアクセル・ブレーキ操作ができる。指を引っ掛ける程度ですから、そこまで握力もいりません。
二宮: 操作が簡単であれば、利用するハードルが下がりますからね。このデバイスがあれば、車椅子を利用する人の移動の自由度が各段に広がりますね。
神村: これまでは私自身の経験があったので、自動車で移動することに固執していた部分がありました。だが現実は障がいのある人を含め自動車を運転しない人の方が圧倒的に多い。逆に言えば、弊社としても自動車を運転しない方の移動を助ける製品がなかった。手動車椅子用の着脱式電動アシストを製造・販売することで、移動格差を解消できる範囲が広がったと思っています。目的地に自分ひとりで向かえることで社会が広がります。やはり人に手伝ってもらわないといけないとなると、相手のことを気遣うストレスが生まれてしまう可能性がありますからね。まず着脱式電動アシストを全国に普及していくことに力を入れようと思った理由です。
(後編につづく)
<神村浩平(じんむら・こうへい)プロフィール>
株式会社ニコ・ドライブ代表取締役。1984年1月7日、神奈川県川崎市生まれ。16歳のときに交通事故で脊髄を損傷し、車椅子生活となる。その頃に出合った車椅子バスケットボールをはじめた。2004年、NECエレクトロニクス株式会社入社。2年後に車椅子バスケットボール選手としてアメリカ留学。2009年、パークランドカレッジの準学士号取得。帰国後、ゴールドマン・サックス証券株式会社に入社。2013年に本田技研工業株式会社のエンジニアだった荒木正文氏とニコ・ドライブを創業し、その2年後に同社を法人化した。
株式会社ニコ・ドライブ
(構成・杉浦泰介)